インターンの探し方完全ガイド|情報源の使い分けから失敗しない進め方まで徹底解説
「インターンに参加したいけど、どうやって探せばいいの?」
就活を始めたばかりの大学生が最初にぶつかるのが、この疑問です。
本記事では、インターン探しの基本ステップから情報源の使い分け方、失敗しないためのコツまでをわかりやすく解説します。効率的に探す方法を知って、自分に合ったインターンを見つけましょう。
▼目次
インターンシップとは?
インターンシップとは、学生が企業で実際の業務を体験できる制度です。企業によって内容や期間は異なりますが、1日から2週間程度の「短期インターン」、そして数か月から1年以上継続して働く「長期インターン」の2種類があります。
このうち、就職活動の一環として多くの学生が参加するのは「短期インターン」です。多くの場合、2〜3日程度の期間で開催され、夏休みや冬休みといったまとまった時期に集中して実施されます。企業もこのタイミングで学生との接点を作ることを重視しており、就活準備の重要なステップになっています。
短期インターンで何をするか
短期インターンでは、その企業の業務をワークショップ形式で体験するのが一般的です。
たとえばグループワークを通じて新規事業の企画を考えたり、ケーススタディを用いて経営課題の解決策を検討したりと、実際の仕事に近いテーマが設定されます。こうした体験を通じて、学生は企業のビジネスモデルや働き方を疑似的に学び、社員との交流を通じて企業文化に触れることができます。
また、メーカーやインフラ関連の企業などでは、工場や設備の見学をプログラムに組み込むケースもあります。現場の雰囲気やスケール感を体感することで、事業内容への理解が一層深まり、就活サイトやパンフレットだけではわからないリアルな情報を得ることができます。
インターンを実施する目的
学生目線
学生にとってインターンの目的は、業界や企業の情報を一次データとして直接取りに行くことです。就活サイトや企業HPといった二次情報は、発信側の意図が強く反映されており、判断材料としては限界があります。
一次データを自分の目と耳で確かめることで、まず「納得して新卒入社先を選べる」ようになります。現場での雰囲気や社員の考え方を知ることで、その企業が本当に自分に合っているかどうかを具体的に判断できるからです。
さらに、インターン経験は「自分だけのオリジナルな志望動機」を作る材料になります。公式情報の受け売りではなく、自分が体験したこと・感じたことを語れるため、選考での説得力が高まり、個性を発揮しやすくなります。
企業目線
企業にとってインターンは重要な接点形成の機会です。特に、夏と冬のインターンでは目的が少し異なります。
夏インターンは、ビジネス感度の高い学生との出会いを重視しています。グループワークやケーススタディを通じて、論理的思考力やチームでの発言力などを観察し、「将来のリーダー候補」を早い段階で見極めたいという狙いがあります。企業にとっては、優秀層と早めに関係を築くことができ、学生にとっても業界全体を広く知るきっかけになるのが特徴です。
一方、冬インターンは、自社にマッチする学生を探す意味合いが強くなります。少人数で社員と密に接するプログラムが多く、学生の人柄や価値観が企業文化に合うかどうかを確かめやすいのです。同時に学生側も「自分にとって働きやすい環境か」を深く理解できるため、双方にとってミスマッチを防ぐ場になっています。
インターン探しのステップ|基本的な進め方
インターン探しは、なんとなく情報を眺めているだけでは効率が悪く、気づいたら応募締切が過ぎていた…ということになりがちです。そこでおすすめなのが、次の4ステップで進める方法です。
① 気になる企業リストを作る → ② インターネットや説明会で情報収集 → ③ インターンに応募 → ④ 選考を受ける
この流れを押さえておけば、インターン探しに迷子にならずに行動できます。
ステップ① 気になる企業リストの作成
まずは「自分が知っている企業」を10社ほど書き出してみましょう。難しく考える必要はなく、普段目にする大手企業や、友人・家族から聞いたことのある会社でOKです。
次に、その企業と関連のある会社をインターネットや『会社四季報』『日本経済新聞』などから調べて、リストを広げていきます。
作成したリストは、以下のように優先順位をつけるのがポイントです。
・すぐにでもインターンに応募したい
・説明会に参加したい
・時間があれば話を聞いてみたい
・今はあまり興味がない
最終的に、リストには100社程度を載せ、そのうち「すぐにでも応募したい」「説明会に参加したい」と思える企業が30社前後ある状態が理想です。
とはいえ、いきなりそれだけの規模のリストを作るのは大変なので、まずは10社程度リストに書き加えましょう。
コツは「考えすぎずにとにかくリストアップすること」と、「新しい企業を知れること自体を楽しむこと」です。
なお、就活イベントなどで新しい企業を知ったら随時このリストに追加します。
ステップ② インターネット・説明会で情報収集
気になる企業を見つけたら、次はインターネットや説明会で「初期接点」を持ちましょう。
特にインターンには選考があるため、企業がどんなビジネスをしているのかをある程度理解しておくことが大切です。公式HPや採用ページ、説明会では、企業が「これだけは知っておいてほしい」という基本情報を整理して伝えてくれます。ここに触れておくことで、応募の際にも自分の理解が整理されやすくなります。
ただし、インターンはすべての企業で参加できるわけではありません。時間的な制約もあるため、実際に参加できるのは5〜8社、多くても20社程度が現実的です。そのためにも、まずはリストアップした企業を対象に、手軽に得られる情報から集めて優先順位を固めていくことが重要です。
ステップ③ インターンに応募する
ある程度企業の理解が深まったら、実際にインターンへ応募してみましょう。
インターンの応募は「とりあえず動いてみる」ことが大事です。なぜなら、エントリーシートや面接の経験そのものが練習になり、次に応募するときに改善できるからです。
応募する際には以下の点を意識してください!
・志望動機は完璧でなくても大丈夫。まずは書いて提出する
・1社だけに絞らず、複数企業に同時並行で応募する
・応募要項の締切日や提出方法をリスト化して管理する
特に大学3年生の夏・冬はインターン募集が集中するため、「気づいたら締切が過ぎていた」というのが最も多い失敗です。気になる企業は、早めにエントリーしておくことを心がけましょう。
ステップ④ 選考を受ける
多くのインターンでは、エントリー後に以下のような選考プロセスがあります。
・書類選考(ES)
・適性検査/Webテスト
・面接(個人・グループ)
・グループディスカッション(企業によっては実施)
・インターン本番
本選考に近い流れで進むケースも多いため、ここでの経験がそのまま就活準備につながります。
【選考を受けるときの考え方】
インターンの選考に臨む際は、次の3点を意識するのがおすすめです。
①選考結果に過度に一喜一憂しない
インターンは「選抜」要素が強いため、倍率が高く落ちることもよくあります。しかし、インターンに参加したことで選考が有利に進むことはあれども、インターン選考に落ちたことで選考が不利に進むことはありません。不合格でも落ち込む必要はなく、より自分の魅力が伝わる方法を模索することに時間を使ってください。
②本選考のために「選考慣れ」しておく
エントリーシートの書き方や面接での受け答えは、繰り返すほど上達します。むしろインターン選考は、本選考に向けた実践練習の場と考えると気持ちが楽になります。
③企業との接点を持ち続ける意識を持つ
インターン選考に落ちても、企業からはメールやイベント案内が届き続けるケースが多いです。「接点を絶やさない」ことで、後々の本選考で有利に働く可能性もあります。
このように、インターンの選考は単なる合否判定ではなく、「経験を積みながら企業との接点を増やすチャンス」 と捉えることが重要です。
インターン探しの基本
インターン探しは、情報をどれだけ効率的に集められるかで成果が大きく変わります。限られた募集枠を逃さず、自分に合った企業に出会うためには、やみくもに探すのではなく、目的に合わせて最適な情報源を選ぶこと が大切です。
インターンの情報源は大きく分けて4種類あります。
①就活サイト
②企業の公式HP/OB・OG訪問
③SNS・就活コミュニティ
④大学のキャリアセンター
それぞれの特徴と、利用する目的を整理してみましょう。
①就活サイト
リクナビ・マイナビ・Goodfindといった大手就活サイトは、インターン探しの出発点になります。数多くの企業が掲載されており、業界を横断して比較できるのが強みです。
特に役立つのは、企業リストを作るときや説明会などの初期接点を探すときです。まずはここで幅広く情報を集めて、自分が気になる企業を見つけるところから始めましょう。
さらにサイトごとに次のような使い分けができます。
・リクナビ・マイナビ:名前を知っている企業について詳しく調べたり、そこから関連する別の企業を見つけたりするのに適している
・Goodfind:自分がこれまで知らなかった視点から成長企業や難関ベンチャーを知るのに向いている
このように複数サイトを組み合わせることで、「知っている企業を深める」と「新しい企業を発見する」の両方ができ、効率的に企業リストを広げられます。
②企業の公式HP/OB・OG訪問
気になる企業が出てきたら、次に活用したいのが公式HPの採用ページやOB・OG訪問です。
公式HPには、インターンの募集要項や選考フロー、企業が学生に知っておいてほしい情報がまとまっています。エントリーを進める際には必ずチェックしておくべき情報源です。
また、OB・OG訪問を通じて先輩から直接話を聞くことで、公式情報だけでは見えないリアルな職場の雰囲気や体験談を知ることができます。「その企業について深く知りたい」「実際に応募したい」 というときに最適です。
③SNS・就活コミュニティ
企業研究をさらに広げたいときには、SNSや就活コミュニティが役立ちます。
X(旧Twitter)やInstagramでは、企業公式アカウントや人事担当者が最新のインターン情報を発信しています。さらに、学生同士が集まるLINEオープンチャットやDiscordなどのコミュニティでは、インターンに参加した学生の体験談や選考情報が共有されることもあります。
加えて、友人や他大学の学生とのヨコのつながりも重要です。「この企業は選考が早い」「あの説明会は参考になる」といった生の情報を、同じ立場の仲間から得られるのは大きな強みです。
SNSやコミュニティは、特定の企業との接点を多様化させたいとき に活用するのが効果的です。
④大学のキャリアセンター
「そもそも何から始めればいいのか分からない」という段階にいる学生は、まず大学のキャリアセンターに相談してみましょう。大学のキャリアセンターは就活を始めたばかりのひとへのサポート体制が充実しています。ですので丁寧にインターン探しの基礎固めを手伝ってくれます。また学内限定のインターンや提携企業の紹介があり、情報源としての基礎を作ることができます。
大学や高校のつながりを通じて先輩に出会い、体験談を聞くのも効果的です。情報源そのものにイメージが湧かないときの最初の一歩として、キャリアセンターや先輩は非常に頼れる存在です。
よくある失敗と対策
インターン探しは情報も多く、行動のタイミングも限られているため、ちょっとした勘違いや行動の遅れが大きな差につながります。ここでは大学3年生が特に陥りやすい失敗と、その対策を紹介します。
目的を考えずに応募してしまう
インターンが気になりだすと、つい「あれもこれもインターンに応募しなきゃ」と焦って動きたくなります。しかし、目的を整理しないままやみくもに応募すると、参加後に「得られるものがなかった」「ただ忙しくなっただけ」という結果になりがちです。
対策としては、応募前に「何を知りたいのか」「何を得たいのか」を最低限メモしておくことが大切です。たとえば「業界研究のため」「就活スキルを試したい」「長期的なキャリアにつなげたい」など目的を明確にしておけば、選ぶ企業やプログラムの基準がぶれません。
企業説明会や合同説明会に参加したり、AIなどを使って企業分析したりしてしまえば事足りることも多いですので、慌てず進めましょう。
情報収集が遅れて締切に間に合わない
インターンの募集は短期間で締め切られることもあります。特に人気企業の場合、応募が殺到して選考の枠やインターンの参加枠がすぐに埋まってしまうケースも少なくありません。「気づいたときには応募が終わっていた」という失敗はよくあるパターンです。
対策は、定期的に情報収集を習慣化すること。週に1度は就活サイトや企業HPをチェックし、気になる情報はすぐに企業リストに書き留めておきましょう。また、SNSや友人とのヨコのつながりから情報をキャッチできる体制をつくっておくことも有効です。
大学生活が短期インターンだけで終わってしまう
1日や2-3日程度の短期インターンは、就活準備や企業理解の入り口としては有効ですが、業務に深く関われるわけではありません。就活面での成長はあれど、その人の基礎的なスキルや経験に必ずしもつながらないこともあります。
大学3年生・修士1年生の時期は、いろいろな経験を通じて、人として成長できる貴重な時期でもありますから、就活・インターンだけで終わらせてしまうのはもったいないです。
時間の使い方にはシビアになりましょう。大学での学びや長期インターン、旅行などを通じて自分の経験を得ることもしっかり考えてください。
行きたいインターンに行くために、ビジネス基礎力を身に着けよう
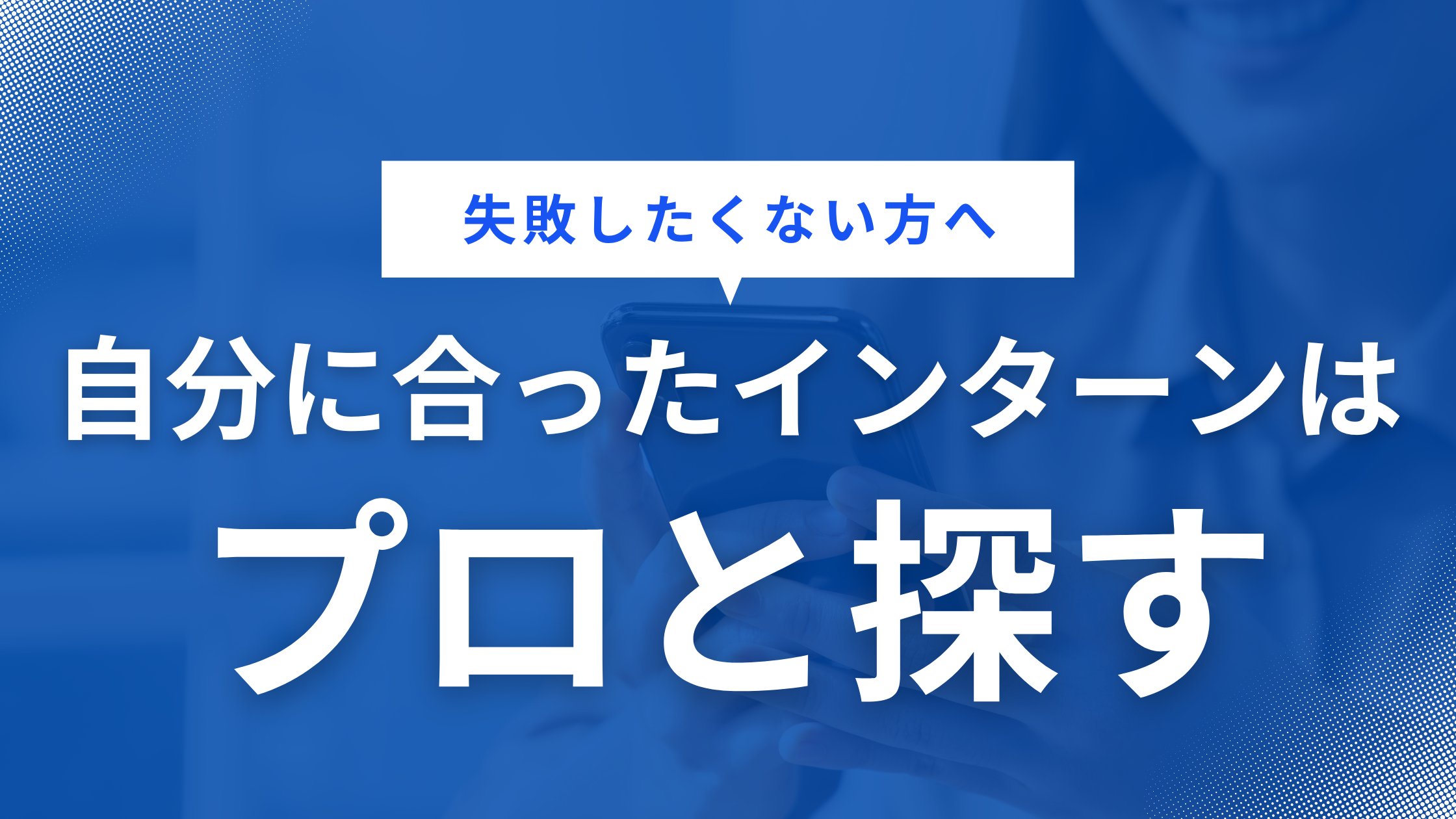
短期インターンは就活準備として有効ですが、人気企業のプログラムは倍率数十倍にのぼり、本選考並みの厳しい選考が行われます。
ESや面接、グループワークで結果を出すには、ビジネスの基礎力や論理的思考力をすでに備えていることが重要です。
しかし、アルバイトや課外活動だけでは「ビジネスの現場で求められる基礎力」を養うのは難しいのが現実です。そこで注目されるのが長期インターンです。
長期インターンとは
長期インターンとは、「有給で長期間(約6ヵ月以上)、実際のビジネスの現場で就業すること」を指します。
大学生でありながら企業に所属し、正社員と同じような業務を任される点が特徴です
多くの企業では、以下のような条件で募集されています。
・週3日以上・週20時間程度の勤務
・最低3〜6ヶ月以上の継続
・業務内容は実際の社員と同じ
ただのおしごと体験ではなく、企業の一員として働きながら成果を出すのが長期インターンです。
行きたいインターンに行くために、ビジネス基礎力を身に着けよう
長期インターンでは、数か月〜1年以上にわたって実務に関わることで、短期インターン選考や本選考に直結するスキルが身につきます。
・論理的に考える力:市場分析や施策立案を通じて、数字やデータを根拠に思考できる
・伝える力:上司やチームメンバーへの報告・提案を繰り返す中で、PREP法的な話法が自然に身につく
・協働力:実務の中で役割分担・合意形成を経験するため、グループワーク選考で強みになる
これらは、まさに短期インターンや就活選考で評価される能力そのものです。
短期インターンへの一番の近道に
短期インターンに挑戦したいと思うなら、事前に長期インターンで基礎力を磨いておくことが合格率を高める最も実践的な方法です。
「選考に挑んだけれど、話す内容が薄くて落ちてしまった…」という事態を避けるためにも、まずは実務経験を積んでおくことが何よりの武器になります。
自分に合った長期インターンを見つけよう

Intern Streetなら、面談を通じてあなたに合った企業を一緒に見つけられます
長期インターンは、一定の時間を投下してビジネス的成長を得る究極の「自己投資」です。そのため自分に合った長期インターンを選ばないと、狙った成果が得られません。
長期インターンを募集する企業は年々増加しています。その中から“自分に本当に合う企業”を自力で見つけるのは、実はとても難しいものです。
「気になる企業はあるけど、実際どんな働き方なのか分からない…」
「長期で続けられるか不安だけど、挑戦はしてみたい…」
「せっかくやるなら、就活にもつながる経験がしたい…」
そんな方にこそ活用していただきたいのが、Intern Streetの無料面談です。
Intern Streetの面談でできること
・目的や希望条件を丁寧にヒアリングし、自分に合う長期インターン先の提案
・志望動機の言語化や選考に進む企業ごとのチューニング
・これまでの経験に応じてレベルを合わせた長期インターン先の紹介
・過去の長期インターン生の経験や工夫の共有
・通常必要なESの代理執筆と選考フォローアップ
・長期インターン選考がうまく行かない際のサポート
自分に合うインターン先を見つけるには、正確な情報と第三者の視点が必要です。迷ったとき、不安なときこそ、私たちと一緒に一歩踏み出してみませんか?

長期インターンについて知りたい場合は15分面談もおすすめです
「長期インターンって実際どんな感じなの?」
そんな方のために、会員登録不要・最短即日で参加できる「15分面談」を実施しています。
この面談では、例えばこんな疑問にお答えします。
・長期インターンでは、どんな働き方をするのか?
・どんな企業がインターンを募集しているのか?
・インターンに参加するための時間の作り方は?
気になることを気軽に相談できる機会です。初めての方も、まずは情報収集から始めてみませんか?

まずはLINEでの適性診断から!
自分に合った長期インターンを探す前に、まずは自分の適性を知ることから始めましょう!就活をまだ始めていない方も、すでに選考を受けている方も、キャリアの軸を見つける最初の一歩として、この診断を活用してください。
①強みの言語化をしてくれる
自己分析だけでは見つけられなかった、あなたの核となる能力をレポートで明確に提示します。
②適職を提示してくれる
「営業」「企画」「エンジニア」といった職種選びだけでなく、
その職種の中でも「どんな役割で」「どんな環境で」最も力を発揮できるかまで具体的に分かります。
③キャリア選択の羅針盤になる
「なんとなく」ではなく、自分の軸を持って長期インターンや就職活動に進むための、最初のヒントが得られます。





