【例文あり】ESで『コミュニケーション能力』を効果的にアピールする方法とは?:企業が求めるコミュニケーションの3つの本質と経験を差別化する例文を紹介
「ESの自己PRで何をアピールしよう…?」そう考えたとき、「コミュニケーション能力」という言葉が頭に浮かぶ学生さんは非常に多いのではないでしょうか。誰とでも分け隔てなく話せること、友人が多いこと、ムードメーカーであること。これらは間違いなく素晴らしい能力です。
しかし、実は就職活動のエントリーシート(ES)で「コミュニケーション能力があります!」とだけ書いても、企業からはほとんど評価されないことをご存知でしょうか。なぜなら、ほぼすべての学生がこのフレーズを使うため、人事の方にとって「差別化できない、抽象的な言葉」になってしまっているからです。
本記事では、ESの自己PRで企業が本当に求めている「コミュニケーション能力」の3つの本質を徹底的に解説し、さらに、他の学生と圧倒的に差をつける具体的なアピール方法と例文をご紹介します。アルバイトやサークル、ゼミなど、学生生活で得た経験をビジネス視点で語り直す方法を習得し、あなたの就活を大きく前進させましょう!
▼目次
そもそも企業はなぜ「コミュニケーション能力」を重視するのか?
企業がコミュニケーション能力を重視する背景には、「ビジネスの構造」と「組織の安定性」という二つの重要な理由があります。
理由①ビジネスはチームでの「目標達成」が基本だから
ほとんどの仕事は、一人では完結しません。上司、同僚、他部署、そして顧客や取引先など、多くの人と関わりながら進めます。このとき、コミュニケーションは単なる会話ではなく、「情報を共有し、目標に向けて認識を統一し、協力して成果を出すための手段」となります。
【企業が避けたいリスク】
指示の誤解:上司の指示を正しく理解できないと、間違ったアウトプットが生じます。
情報連携の滞り:必要な情報がチーム内で共有されないと、プロジェクト全体が遅延します。
高いコミュニケーション能力を持つ人材は、これらのリスクを未然に防ぎ、チームの生産性を高めると期待されるため、企業にとって不可欠な存在なのです。
理由②組織の成長と安定に不可欠な要素だから
コミュニケーション能力は、変化の激しいビジネス環境において、新しいアイデアを生み出し、組織内の風通しを良くする役割も担います。
問題の早期発見:率直に意見を言い合える環境があれば、小さな問題が大きくなる前に解決できます。
多様性の受容:異なる意見を持つ人たちと建設的に議論し、協力し合うことで、より革新的な解決策が生まれます。
つまり、企業がコミュニケーション能力を重視するのは、「円滑な人間関係」のためではなく、「円滑な目標達成」と「組織の健全な運営」のためなのです。だからこそ、ESでは「仲が良い」ではなく、「成果に繋がるコミュニケーション」を示す必要があります。
企業がESで求める「コミュニケーション能力」の3つの本質
企業がESで確認したいのは、「あなたが職場でビジネス上の成果を出すために、コミュニケーションをどう使えるか」という点です。単に「話すのが上手」ではなく、具体的な目的達成に向けた能力が求められます。
企業が特に重視する「コミュニケーション能力」の具体的な要素は、以下の3つに分解できます。
本質①相手の意図を正確に理解し、目標達成に繋げる『傾聴力・受容力』
これは、単に黙って話を聞く能力ではありません。会話の裏にある相手の真のニーズや、発言に至った背景を深く理解する能力です。
例えば、顧客が「新しいシステムが欲しい」と言ったとき、その背景にある「今の業務のどこに不満があるのか」「システム導入で何を解決したいのか」を質問力と傾聴で引き出し、最適な提案に繋げられるかが『傾聴力・受容力』だと言えます。
この能力は、特に営業やコンサルタントなど、人と相対して相手の課題解決を担う職種で求められます。
本質②多様な意見をまとめ、チームを前進させる『調整力・ファシリテーション力』
組織やチームでは、必ず意見の衝突や方向性の違いが生まれます。その際に、自分の意見を通すだけでなく、多様な意見を公平に聞き、それぞれのメリット・デメリットを整理し、チーム全体として最善の落としどころを見つけ出せるかが重要です。
この能力は、チームプロジェクトのリーダーや、部署間の連携を円滑に進めるマネジメント職で特に重要視されます。
本質③目的達成のために論理的かつ簡潔に伝える『発信力・論理的伝達力』
「話す能力」の本質は、論理的に構成された情報を相手が理解しやすいように伝え、行動を促すことです。どれほど良いアイデアを持っていても、相手に伝わらなければビジネスでは意味がありません。
結論から述べ、その根拠を構造的に説明するロジカルシンキングに基づいた発信力は、会議でのプレゼンテーションや上司への報告、お客様への説明など、あらゆるビジネスシーンで不可欠な能力です。
ESでコミュニケーション能力を言い換える際の3つの注意点
ESで抽象的な「コミュニケーション能力」を避けるためには、「コミュニケーション能力」を具体的な言葉に言い換える必要があります。その言い換えを効果的にするために、以下の3つの点に注意しましょう。
注意点①抽象的な「言葉」に逃げない
コミュニケーション能力を言い換える際、「協調性」「人間関係構築力」「コミュ力」といった、結局意味が曖昧な言葉で終わらせてしまうのは避けましょう。
【NGな言い換えの例】
「私の強みは協調性です。」
「私の強みは人間関係構築力です。」
【OKな言い換えの例(行動の型を示す)】
「私の強みは、利害関係の異なるメンバーの意見を統合する『調整力』です。」
「私の強みは、相手の真のニーズを引き出す『質問力・傾聴力』です。」
重要なのは、「あなたがコミュニケーションを通じて何ができるのか」を明確に示すことです。その職場であなたがどういう活躍をしてくれそうか、企業の採用担当者が想像しやすいような表現を用いましょう。
注意点②応募企業の求める人物像と「具体的に」関連づける
言い換える能力は、応募する企業や職種によって最適解が異なります。企業が求める能力と、あなたがアピールする言い換えが一致しているか確認しましょう。
【営業・コンサルタント職を志望する場合】
顧客の真のニーズや潜在的な課題を解決することが求められるため、単に「話がうまい」だけでは不十分です。この職種では、「顧客の課題解決」に繋がるコミュニケーション能力を重視すべきです。
おすすめの言い換え例:傾聴力、質問力、課題特定力
【企画・マーケティング職を志望する場合】
新しいアイデアや施策を社内外の関係者に理解・納得させ、実行に導く必要があります。そのため、「社内外の連携や説得」を可能にするコミュニケーション能力が必要です。
おすすめの言い換え例:論理的伝達力、ファシリテーション力(会議を円滑に進める力)。
【エンジニア・研究開発職を志望する場合】
専門性の高い知識を、技術に詳しくない他部署(営業や企画など)にも分かりやすく正確に伝え、認識のズレを防ぐことが重要です。したがって、「専門知識の共有や他部署との連携」がコミュニケーションの本質になります。
おすすめの言い換え例:情報共有能力、構造化された報告力。
このように、応募する職種の役割を理解した上で、最もフィットする具体的な能力名に言い換えることで、ESの説得力は格段に向上します。
注意点③その能力を発揮した「成果」を必ずセットで語る
いくら優れた能力に言い換えても、その能力がどのような成果に結びついたかがなければ、単なる自慢で終わってしまいます。企業は、あなたの能力が「再現性のある成果」を生むかを評価しています。
【能力と成果のセット例】
「私は自身の『傾聴力』を活かして、クレームの真の要因を特定し、店舗の顧客満足度を○%向上させました。」
「私は自身の『調整力』を活かして、対立するメンバー間の建設的な議論を可能にし、プロジェクトを納期内に完了させました。」
「能力の言い換え」と「具体的な実績」は、常にセットで語ることを意識してください。
ESで「コミュニケーション能力」を最強の武器にするためのステップ
抽象的な「コミュニケーション能力」をESで強力なアピールポイントにするためには、エピソードを深掘する必要があります。具体的な以下の3つのステップを説明します。
ステップ1:具体的なエピソードを「定量的に」絞り込む
「サークルで皆と仲良くした」というエピソードでは、あなたが上記のどの能力を発揮したのか分かりません。目標と結果が明確な、課題解決の経験を選ぶことが重要です。
【弱いエピソード(抽象的)】
・アルバイトで接客に貢献した
・サークルで皆と楽しく活動した
【強いエピソード(具体的・定量的)】
・アルバイトで「お客様の声」分析を行い、リピート率を10%向上させた
・サークルで退会率の課題を特定し、新入生への個別フォローにより退会者を半減させた
ステップ2:課題解決のプロセスで「何を考え、どう行動したか」を深掘りする
企業は「あなた独自の思考と行動の型」を知りたいのです。エピソードを深掘る際は、以下の要素を必ず盛り込みましょう。
●課題/目標(Situation/Task):何を目指し、どんな問題があったか。
●行動(Action):課題に対し、あなたは具体的に何をしたか。(ここが「コミュニケーション能力」の発揮ポイントです)
●思考(Thinking):なぜその行動を選んだのか。どんな意図で、相手にどう伝えたか。(あなたの判断基準を示す)
●結果(Result):その行動がどんな成果を生んだか。
●学び/入社後の活かし方:その経験から何を学び、入社後にどう活かすか。
ステップ3:入社後に「その能力をどう活かすか」を具体的に示す
ESのゴールは「入社後に活躍できるイメージ」を人事に持たせることです。「この経験を通じて磨いた〇〇力を、御社の〇〇部門で、具体的に〇〇という目標達成のために活かしたい」と、再現性を示すことで、ESの説得力は格段に上がります。
経験を差別化する! 学生生活で培ったES例文集
ここからは、特別な経験がない学生でも応用できる、一般的な学生経験をビジネス視点で語り直した例文をご紹介します。
例文1:『傾聴力・受容力』を活かしたアルバイト経験のES
「私の強みは、お客様の言葉にならないニーズを引き出す『傾聴力』です。これは、カフェでのアルバイトで、クレーム対応の際に培いました。
ある日、注文した商品が提供されないというお叱りを受けました。単に謝罪するだけでなく、私はまず『大変申し訳ございませんでした。よろしければ、どういう経緯で不快な思いをされたかをお聞かせいただけますでしょうか』と、状況を全て吐き出していただく姿勢を取りました。この徹底的な傾聴により、お客様が本当に不満に思っていたのは『商品が遅れたこと』ではなく、その後、誰も状況を把握しようとしなかった『対応の不誠実さ』にあると気づきました。
その後、全スタッフに情報の連携と報告を徹底する仕組みを提案し、実行した結果、店舗のアンケートにおける接客満足度が翌月には改善しました。この、相手の真の意図を汲み取り、課題の根本を解決する力は、御社での顧客対応業務においても必ず活かせると確信しております。」
例文2:『調整力・ファシリテーション力』を活かしたサークル活動のES
「私の強みは、利害の異なるメンバーの意見を統合し、最適な解決策を導く『調整力』です。これは、大学の文化系サークルで、オンラインイベントを開催する際のリーダー経験で発揮しました。
企画段階で、集客を重視するメンバーは『誰もが知る有名人を呼ぶべき』と主張し、費用対効果を重視するメンバーは『コストを抑えて内輪で完結すべき』と対立しました。私は、まず両者の意見を『メリット(知名度)とデメリット(予算)』という軸で整理し、『予算内で最大の知名度を得る』という共通の目標を再定義しました。
その上で、有名人ではなく、SNSでフォロワーの多いOG/OBに依頼するという妥協案を提案し、双方から納得を得ました。この調整により、企画は無事進行し、集客目標の120%を達成することができました。」
例文3:『発信力・論理的伝達力』を活かしたゼミ・授業での経験のES
「私の強みは、専門的な内容を相手に理解させる『論理的伝達力』です。これは、経済学のゼミで、難解な論文の内容をチームメンバーに共有する役割を担った際に磨かれました。
初めてのディスカッションで、専門用語をそのまま使った説明が原因で、メンバーの理解度がバラバラになってしまいました。そこで私は、論文の解説を行う前に、『本日のゴールは何か(結論)』をまず明示し、複雑な概念は『図解』や『日常生活での具体例』に置き換えて説明するプロセスを導入しました。
この構造化された発信を徹底した結果、チーム内での質問の質が向上し、教授から『最もスムーズで建設的なディスカッション』と評価されるようになりました。この、相手の理解度を常に意識し、情報を構造化して伝える力は、御社での社内報告やクライアントへの説明において貢献できると確信しております。」
注意点:これらの経験をさらに強力にする方法
アルバイトやサークルでの経験を上記のようにビジネス視点で語り直すことは非常に重要です。しかし、これらの経験はあくまで「非営利」または「指示された業務」の範囲に留まりがちで、自己PRの説得力に限界があるのも事実です。
もしあなたが、さらに就職活動で頭一つ抜け出したい、「ビジネスの現場で培った」という実績で圧倒的な差をつけたいとお考えであれば、長期インターンシップを強くお勧めします。
長期インターンを通じてビジネス基礎力を身に着けよう
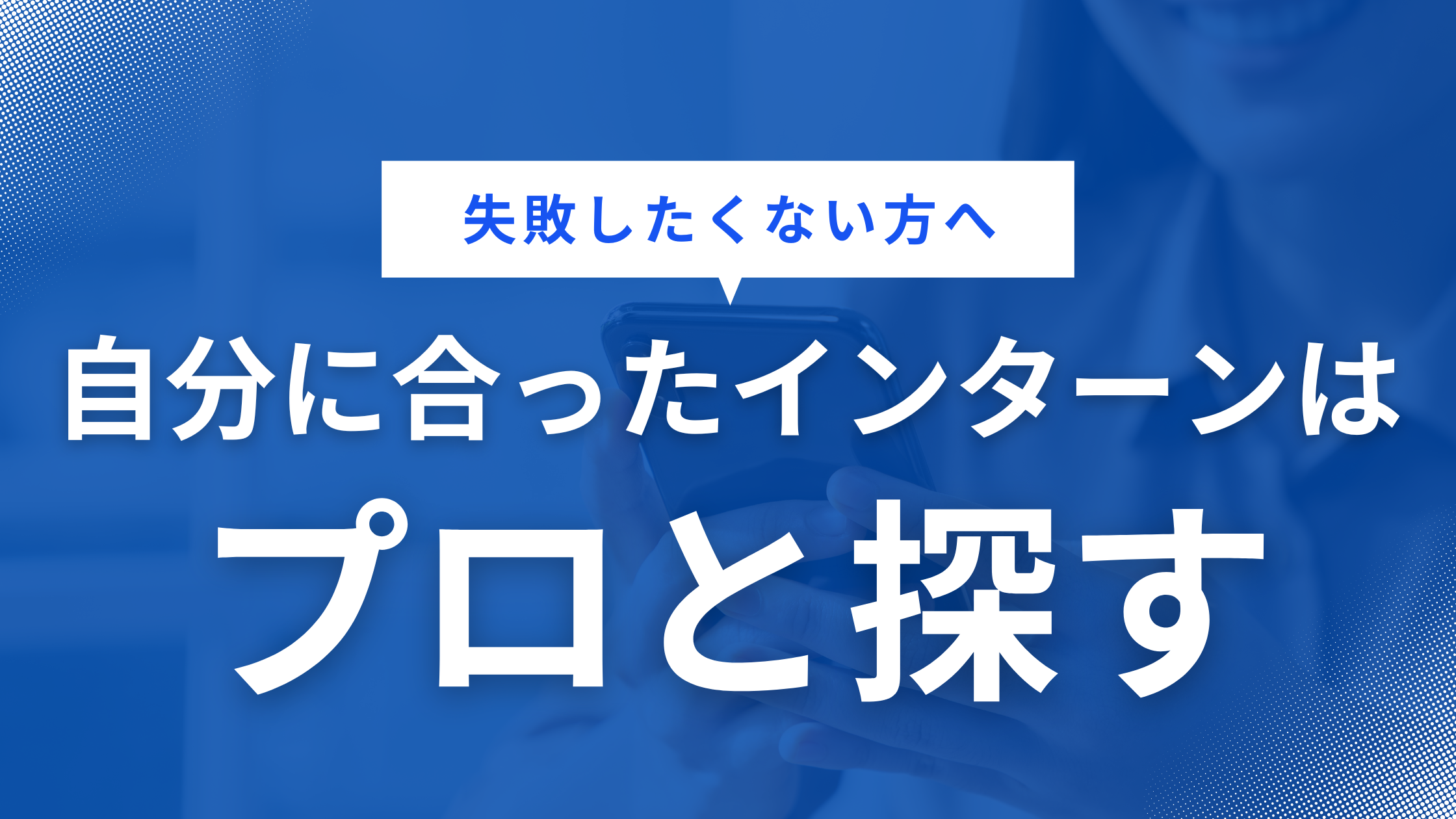
長期インターンとは
長期インターンとは、「有給で長期間(約6ヵ月以上)、実際のビジネスの現場で就業すること」を指します。
大学生でありながら企業に所属し、正社員と同じような業務を任される点が特徴です
多くの企業では、以下のような条件で募集されています。
・週3日以上・週20時間程度の勤務
・最低3〜6ヶ月以上の継続
・業務内容は実際の社員と同じ
ただのおしごと体験ではなく、企業の一員として働きながら成果を出すのが長期インターンです。
行きたいインターンに行くために、ビジネス基礎力を身に着けよう
長期インターンでは、数か月〜1年以上にわたって実務に関わることで、短期インターン選考や本選考に直結するスキルが身につきます。
・論理的に考える力:市場分析や施策立案を通じて、数字やデータを根拠に思考できる
・伝える力:上司やチームメンバーへの報告・提案を繰り返す中で、PREP法的な話法が自然に身につく
・協働力:実務の中で役割分担・合意形成を経験するため、グループワーク選考で強みになる
これらは、まさに短期インターンや就活選考で評価される能力そのものです。
短期インターン・本選考での成功への一番の近道に
短期インターン・本選考で良い結果を出したいと思うなら、事前に長期インターンで基礎力を磨いておくことが最も実践的な方法です。
「選考に挑んだけれど、話す内容が薄くて落ちてしまった…」という事態を避けるためにも、まずは実務経験を積んでおくことが何よりの武器になります。
自分に合った長期インターンを見つけよう

Intern Streetなら、面談を通じてあなたに合った企業を一緒に見つけられます
長期インターンは、一定の時間を投下してビジネス的成長を得る究極の「自己投資」です。そのため自分に合った長期インターンを選ばないと、狙った成果が得られません。
長期インターンを募集する企業は年々増加しています。その中から“自分に本当に合う企業”を自力で見つけるのは、実はとても難しいものです。
「気になる企業はあるけど、実際どんな働き方なのか分からない…」
「長期で続けられるか不安だけど、挑戦はしてみたい…」
「せっかくやるなら、就活にもつながる経験がしたい…」
そんな方にこそ活用していただきたいのが、Intern Streetの無料面談です。
【Intern Streetの面談でできること】
・目的や希望条件を丁寧にヒアリングし、自分に合う長期インターン先の提案
・志望動機の言語化や選考に進む企業ごとのチューニング
・これまでの経験に応じてレベルを合わせた長期インターン先の紹介
・過去の長期インターン生の経験や工夫の共有
・通常必要なESの代理執筆と選考フォローアップ
・長期インターン選考がうまく行かない際のサポート
自分に合うインターン先を見つけるには、正確な情報と第三者の視点が必要です。迷ったとき、不安なときこそ、私たちと一緒に一歩踏み出してみませんか?

長期インターンについて知りたい場合は15分面談もおすすめです
「長期インターンって実際どんな感じなの?」
そんな方のために、会員登録不要・最短即日で参加できる「15分面談」を実施しています。
この面談では、例えばこんな疑問にお答えします。
・長期インターンでは、どんな働き方をするのか?
・どんな企業がインターンを募集しているのか?
・インターンに参加するための時間の作り方は?
気になることを気軽に相談できる機会です。初めての方も、まずは情報収集から始めてみませんか?

まずはLINEでの適性診断から!
自分に合った長期インターンを探す前に、まずは自分の適性を知ることから始めましょう!就活をまだ始めていない方も、すでに選考を受けている方も、キャリアの軸を見つける最初の一歩として、この診断を活用してください。
①強みの言語化をしてくれる
自己分析だけでは見つけられなかった、あなたの核となる能力をレポートで明確に提示します。
②適職を提示してくれる
「営業」「企画」「エンジニア」といった職種選びだけでなく、
その職種の中でも「どんな役割で」「どんな環境で」最も力を発揮できるかまで具体的に分かります。
③キャリア選択の羅針盤になる
「なんとなく」ではなく、自分の軸を持って長期インターンや就職活動に進むための、最初のヒントが得られます。





